 ギャガ株式会社:映画宣伝・マーケティングサポートスタッフ
ギャガ株式会社:映画宣伝・マーケティングサポートスタッフ- 【注目!!】株式会社サンライズ社:コメンタリー副音声 提案進行、映画タイアッププランニング業務
- 【注目!!】株式会社マンハッタンピープル:①パブリシスト(WEB/電波/プリント)②宣伝プロデューサー
- 【注目!!】株式会社フラッグ:①パブリシスト(オフライン)②広告プランナー
- 【注目!!】株式会社K2 Pictures:①配給 劇場営業(セールス)②宣伝(プロデューサー、AP、制作宣伝)③総務・経理(デスク担当)
- 【注目!!】松竹ナビ株式会社:①映画宣伝②アドバタイジング業務
- 【注目!!】株式会社アマゾンラテルナ:ライブビューイング(コンサート・舞台・イベントや映画作品舞台挨拶の映画館への生中継)の制作担当者
- 【注目!!】映画ランド株式会社:(1)セールス(映画館向けSaaSシステムの営業 / インサイドセールスメイン)(2)カスタマーサポート(映画館向けSaaSシステムの営業 / カスタマーサクセス職候補)(3)経理・財務担当 (CFO候補)
人気記事デイリーランキング:26年01月12日集計
エンタメ・トピックス
最新記事
日中合作映画『空海』を製作総指揮、角川歴彦KADOKAWA取締役会長に聞く
2018年01月30日
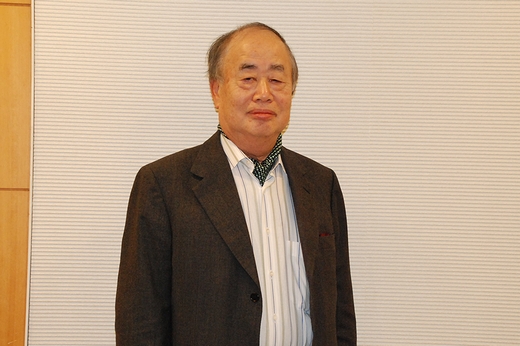
総製作費150億円、空前絶後の超大作プロジェクト、日中合作、夢枕獏原作、チェン・カイコー監督―――。そんな巨大な触れ込みで始まった映画『空海―KU‐KAI― 美しき王妃の謎』が、ついに完成した。
時は、今から1200年以上前。遣唐使として若き僧侶・空海は中国・唐へ渡る。当時世界最大の都・長安では、権力者が次々と奇妙な死を遂げる怪事件が発生。空海は詩人・白楽天(のちの白居易)とともに事件を探るうちに、50年前に唐へ渡った日本人・阿倍仲麻呂、仲麻呂が仕えた玄宗皇帝、その寵愛を受けた楊貴妃に行き当たる。極楽の宴、怪猫の呪い、楊貴妃をめぐる真実に、空海と白楽天は立ち向かう。
企画の立ち上げから関わり、製作総指揮として陣頭指揮をとる角川歴彦KADOKAWA会長(=写真)は、渾身の作品の完成を見届けて、いま何を語るのか。
夢枕獏原作の長編伝奇小説、チェン・カイコー監督を説得
企画の立ち上げは、今から10年ほど前にさかのぼる。夢枕獏の長編小説「沙門空海唐の国にて鬼と宴す」(角川文庫/徳間文庫)が出版されたのは2004年。原作は8~9世紀、中国の盛唐から中唐の時代を舞台に、空海をはじめとする多彩な登場人物が現れ、壮大なドラマを繰り広げる伝奇小説だ。文庫本で4冊、2千ページもある大長編の映画化に、角川氏は『始皇帝暗殺』以来、親交を深めるチェン・カイコー監督を指名した。
角川 このプロジェクトを始めて、もう10年になるんですよ。まず獏さんの原作がよかったから、これを映画化したい。もう1つは、チェン・カイコー監督とどうしても一緒にやりたかった。その2つを重ねることが僕の眼目でした。監督は角川さんと一緒にやるのはいいけど、盛唐の楊貴妃をテーマにするのはもう手垢がついてるから嫌だって。僕は、盛唐の時代の、玄宗皇帝と楊貴妃の極楽の宴をチェン・カイコーの手でやるべきだと説得してね。獏さんも何回か中国に同行して、説得してくれました。そんな時、監督の妻で女優のチェン・ホンさんが、角川さんと一緒にやることが大事だからやりましょうよって。結果的に監督のモチベーションになったのは、最初は嫌だと言っていた極楽の宴であり、完成した作品は極上のシーンになりました。
夢枕獏の原作は、2千ページの大長編をぐいぐい読ませる。そんな力がある。
角川 獏さんの原作の素晴らしいのは、どこにも嘘がないこと。残っている歴史的事実を全部踏まえてます。実際に空海が唐にいた期間はそのとおりだし、青龍寺というお寺から灌頂(かんじょう、密教で修行を終えた僧に阿闍梨の位を許すための儀式)を受けたのも事実です。それら事実と事実をフィクションでつないでいく。その点、本当によくできた小説で、監督は「獏さんの小説、僕は100回も読んだんだから、内容については一番詳しんだ」って威張ってるんです(笑)。
はじめ台湾で中国語版の原作「沙門空海」が出て、中国で売れて、今はなんと「陰陽師」が大ブーム。陰陽師のゲームがバカ当たりしてるんです。ところが陰陽師は一般名詞だから、中国で商標権が取れないですって。陰陽師の映画が目下3本進んでるらしいけど、商標権がないから獏さんはお金をもらえないかもしれない(笑)。でも明らかに獏さんの小説「陰陽師」に依っている。獏さんはいま中国で、「沙門空海」でベストセラー作家として認められて、ゲームの原作者として知らない人はいないほど。そして昨年末に『空海―KU‐KAI― 美しき王妃の謎』(中国語タイトル:妖猫伝)が公開され、獏さんにとってとてもいい回転をしていますね。
脚本、政治…苦難の10年
苦難つづきの映画製作だった。脚本は書き直しを重ねた。音楽も難航。日中の政治問題も大きく影響した。
角川 監督がチェン・カイコーに決まってまずは軌道に乗ったんだけど、その後もいろいろと大変でしてね。例えば脚本。何回も書き直しました。最初は日本の脚本家を起用し、監督と数日間打合せしながら作ったけれど、監督はそれを捨て、その次も捨てて、最終的には『グリーン・デスティニー』の脚本家(ワン・フイリン)が入って、それが完成稿に。ところが監督は、今度は自分で手直しをして。脚本に対するこだわりはすごいなと圧倒されました。
角川氏が脚本に関して、いくつもアイデアを出している。
角川 僕も、脚本の段階でアイデアを出しました。日本の監督もそうですが、一流監督になると、僕あたりが難点を言うとそれを単に受け入れるんじゃなく、自分で消化して形を変えて吸収する。それが、今回の脚本に表れていました。例えば極楽の宴のシーンは僕がもっと派手にしようと提案したところであり、この素晴らしさをぜひ見てもらいたい。それから猫の描写です。玄宗皇帝と楊貴妃が可愛がった猫が楊貴妃の気持ちを受け止めて、復讐していくという筋書きです。猫が人間に変わる瞬間と、猫である瞬間が影絵で出てきます。僕は、監督に日本の江戸時代の怪猫絵の話をしました。行燈に猫が映って、美人が油を吸うとヒューっといって顔を上げた時にはキレイな顔が口まで裂けている。子どもの頃に怖かった怪猫絵の話をしたところ、明らかに僕が言ったことにインスパイアされて屏風や襖に猫の影が何回も出ています。極楽の宴のシーン、猫の影絵の2つは、僕のアイデアを監督が取り入れてくれました。
中国語タイトルが『妖猫伝』というように、楊貴妃が可愛がっていた猫をいかに本物らしく見せるか。その表現力が問われた。
角川 猫は、まったくCGです。これを手がけたのは日本の映像制作会社、オムニバス・ジャパン。猫の毛の動きを表現するのは大変なことですが、映画の中の猫にはリアリティがあって、日本のCG技術は進化しているんだと驚かされました。世界的水準だと監督も太鼓判を押しています。最後の方で人間と猫の目が同一化してきて、猫なのか人間なのかわからなくなってくる。猫が悲しそうな顔をするシーンで、きっと猫ファンは泣きますよ。
主役は空海、仲麻呂、白楽天、中国語なし、高橋一生ら吹替え
膨大な量の原作から、何を抽出するか。原作と映画では主人公が異なる。原作は空海と、空海・嵯峨天皇と並ぶ三筆であり唐では儒学生だった橘逸勢の2人。映画には逸勢は登場せず、原作で逸勢が務めた役回りを白楽天に負わせ、空海と白楽天がバディとなって謎解きに奔走する。
角川 逸勢の役目を白楽天にしたのは監督の考えで、これは成功しています。原作で逸勢は最後まで逸勢でしかないんだけど、白楽天は玄宗皇帝と楊貴妃のエピソードを題材にした「長恨歌」を作っている最中で、そんな白楽天に件の猫が楊貴妃の死にまつわる真実を知らせようと寄ってくる。ここは、監督のアイデアが光っています。
続きは、文化通信ジャーナル2018年2月号に掲載。

