- 【注目!!】株式会社KADOKAWA:セールス・インシアター募集/映像コンテンツの配給営業、インシアター業務
- 【注目!!】株式会社フラッグ:①パブリシスト(オフライン)②広告プランナー
- 【注目!!】株式会社ハピネット・メディアマーケティング:ハピネットファントム・スタジオ劇場営業チームスタッフ
- 【注目!!】松竹株式会社:洋画等の海外映像コンテンツの買い付けメンバー
- 【注目!!】株式会社K2 Pictures:①配給 劇場営業(セールス)②宣伝(プロデューサー、AP、制作宣伝)③総務・経理(デスク担当)
- 【注目!!】日活株式会社:①映画・映像宣伝プロデューサー(管理職候補/正社員)②映画・映像宣伝プロデューサー(スタッフ職/契約社員)
- 【注目!!】松竹ナビ株式会社:①映画宣伝②アドバタイジング業務
- 【注目!!】株式会社アマゾンラテルナ:ライブビューイング(コンサート・舞台・イベントや映画作品舞台挨拶の映画館への生中継)の制作担当者
- 【注目!!】松竹株式会社:映画宣伝部 宣伝雑務
- 【注目!!】mov株式会社:① コンテンツ調達 (ライセンス営業)
- 【注目!!】映画ランド株式会社:(1)セールス(映画館向けSaaSシステムの営業 / インサイドセールスメイン)(2)カスタマーサポート(映画館向けSaaSシステムの営業 / カスタマーサクセス職候補)(3)経理・財務担当 (CFO候補)
人気記事デイリーランキング:25年12月06日集計
エンタメ・トピックス
最新記事
特集:第2回声優アワード授賞式
2008年03月19日
(ページ2/3)
■パーソナリティ賞 (ラジオ、テレビなどの番組のパーソナティティとして活躍した人)

鈴村 健一
「(有)チェリーベル」など、数々の番組のパーソナリティとして活躍。独特の語り口と、そのギャグセンスでリスナーを魅了し続けている。声優としても数々の番組でその存在感を際立たせており、現在のアニメシーンには欠かせぬ存在である。
「2007年は声優の名前が広がっていくことが良いことだと思って活動してきました。この業界も大きく広くなってほしいです。」
■歌唱賞 <プレゼンター:文化放送片寄編成部長>

「もってけ!セーラーふく」
テレビアニメ「らき☆すた」のOP曲として発表された「もってけ!セーラーふく」。その遊び心の高い音楽性がファンに高く評価され、CDとして発売されると、初登場でオリコン2位を記録。現在では20万枚以上を出荷し、アニソン史上に残る超大ヒット作品となる。
平野綾「このメンバーでこの賞をもらえてとっても嬉しいです。」
加藤英美里「4人で受賞できたことが本当にうれしいです。」
福原香織「応援してくださった皆様のおかげです。ありがとうざいました。」
遠藤綾「驚くほど沢山の方の耳と記憶に残る曲で嬉しいです。」
■シナジー賞 (作品として声優の魅力を最大限に発揮したもの)

「仮面ライダー電王」
2007年1月~2008年1月放送。斬新な設定が話題を呼び、一躍大ヒット。関・遊佐・てらそま・鈴村の4人で歌う「Climax Jump DEN-LINER form」はオリコン初登場2位を記録し、社会現象となる。4月には劇場版第二弾が公開される。
関俊彦「1年間愛してくれた全てのキャスト、スタッフに感謝します。」
遊佐浩二「制作陣、縁者の熱意を感じる作品でした。」
てらそままさき「この4人で時間を共有できたのは嬉しいです。」
鈴村健一「まさか自分が仮面ライダーになれると思いませんでした。賞をもらえて嬉しいです。」
■特別功労賞 (外画を含め多くのジャンルで活躍・貢献した故人)


城 達也 (左写真)
グレゴリー・ベックやロバート・ワグナー等の外画の吹き替えなどで絶大な人気を集めた。アニメ作品では「忍風カムイ外伝」「妖怪人間ベム」などのナレーションを担当。TOKYO FM(開始当初はFM東海)「ジェットストリーム」の初代パーソナリティとして、その美しく心安らぐ声で、多くの人を魅了した。
篤美夫人(右写真右)「先月亡くなって13年を迎えました。ますます声優の皆さんのご活躍ご発展をお祈りしています。受賞は主人にも伝えておきます。」
■功労賞 (長年にわたり外画を含め多くのジャンルで活躍した人)

野沢 那智 (写真左)
声優業界大御所の一人として知られ、数多くの洋画吹き替え・アニメ作品で声の出演を果たす。外画ではアラン・ドロンなどの二枚目役や「ダイ・ハード」のブルース・ウィリスの吹替を勤めた。「悟空の大冒険」の三蔵法師役、「エースをねらえ!」の宗方仁役などがある。
「アル・パチーノ、アラン・ドロン、ブルース・ウィリス…大スターをやらせて頂きました。名優の先輩に囲まれていたことに最近気づきました。功労賞の力が発揮できたか疑問なので、もう一度考え直さなければならないと思っています。」
羽佐間 道夫 (写真中央)
5,000本を超える外画の吹き替えをこなし、シルヴェスター・スタローンやマイケル・ケイン、ハリソン・フォードそしてロバート・デニーロと幅広い芸域で大役の数々を担当。アニメ作品も「MONSTER」「スターウォーズ~クローン大戦~」「銀河英雄伝説」「ガラスの艦隊」などに出演している。
「先日82歳の女性からファンレターを頂きました。これが功労賞の所以でしょうか…。まだどこまでいけるか分かりませんが、頑張っていきたいです。」
来宮 良子 (写真右)
5,000本を超える外画の吹き替えをこなし、シルヴェスター・スタローンやマイケル・ケイン、ハリソン・フォードそしてロバート・デニーロと幅広い芸域で大役の数々を担当。アニメ作品も「MONSTER」「スターウォーズ~クローン大戦~」「銀河英雄伝説」「ガラスの艦隊」などに出演している。
「私ももうすぐ82歳(?)。これからもなんとか頑張ってやっていきたいと思います。」
■富山敬賞(話題賞) (新設/声優という職業を各メディアを通して多く広めた人)
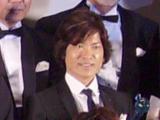
古谷 徹
近年は海外でのイベントに精力的に参加するなど、国内外で声優の魅力を広めた事に対して特に注目を集めた。08年は声優生活40周年。代表作として「機動戦士ガンダム」アムロ・レイ役、「巨人の星」星飛雄馬役、「聖闘士星矢」ペガサス・星矢役など。
「長年ヒーロー声優を演じてきました。富山敬さんは第一線のヒーローの大先輩。この名前を冠した賞を頂き、感無量です。賞の名に恥じぬよう、少しでも海外との交流活動などで功績を残し、いつの日か『古谷徹賞』ができるように頑張っていきたいです。」
(ページ2/3)

