 有限会社ミラクルヴォイス:宣伝プロデューサー、パブリシティ、宣伝部アシスタント、デスク
有限会社ミラクルヴォイス:宣伝プロデューサー、パブリシティ、宣伝部アシスタント、デスク 東映株式会社:映像プロデューサー
東映株式会社:映像プロデューサー 株式会社ULM(ウルム):SNSプロモーションプランナー
株式会社ULM(ウルム):SNSプロモーションプランナー- 【注目!!】株式会社アマゾンラテルナ:ライブビューイング(コンサート・舞台・イベントや映画作品舞台挨拶の映画館への生中継)の制作担当者
- 【注目!!】アイマックスジャパン株式会社:Associate Manager, Local Language Marketing アソシエイトマネージャー、ローカルランゲージマーケティング
- 【注目!!】mov株式会社:①コンテンツビジネス法務担当②コンテンツ海外販売・流通担当③字幕翻訳・ローカライズ担当④国際事業統括マネージャー⑤財務担当 ※CFO候補⑥事業推進マネージャー ※COO候補
- 【注目!!】株式会社クロックワークス:制作アシスタント
- 【注目!!】株式会社フラッグ:①パブリシスト(オフライン/オンライン)②デジタルプロモーションプランナー③広告プランナー④デスク
- 【注目!!】株式会社K2 Pictures:①配給 劇場営業(セールス)②宣伝(プロデューサー、AP、制作宣伝)③総務・経理(デスク担当)④商品化担当
- 【注目!!】松竹ナビ株式会社:①映画宣伝②アドバタイジング業務
- 【注目!!】映画ランド株式会社:(1)セールス(映画館向けSaaSシステムの営業 / インサイドセールスメイン)(2)カスタマーサポート(映画館向けSaaSシステムの営業 / カスタマーサクセス職候補)
インタビュー
最新記事
特集 東宝のゴジラ戦略
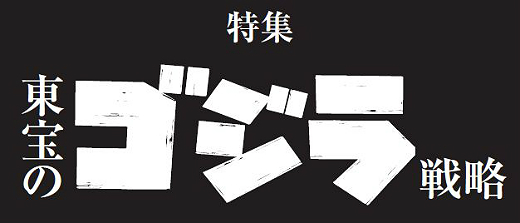
邦画と洋画、実写とアニメを問わず、大作、話題作がひしめいた2016年の夏興行。下馬評を覆してトップを制したのは、東宝が製作・配給した『シン・ゴジラ』だった。2年前のハリウッド版『GODZILLA ゴジラ』があげた興収32億円が一つの目安になると思われたが、結果はその2倍を大きく上回り、10月16日現在で77億8千万円を記録。80億円突破が目前に迫り(11月16日に突破)、さらなるロングラン興行が見込まれている。
日本で製作されたゴジラとしては29作目となった『シン・ゴジラ』は、総監督に庵野秀明という稀代のクリエイターを得て、60年を超えるゴジラの長い歴史において、新たな領域を切り開いた。
東宝が製作するゴジラは、04年12月公開の『ゴジラ FINAL WARS』以来だった。前作の12年前には想像もできなかったほど加速度的に普及したネット社会を背景に、公開初日まで情報統制が敷かれていた『シン・ゴジラ』を取り巻く熱気は一気に拡散。作品に対する圧倒的な高評価と、観客自らが発信源となるSNSが相乗的に効果を発揮。リピーターの続出、女性層の獲得といった過去のゴジラにはなかった様々な展開をみせ、まさに社会現象という事態にまで発展した。16年の映画界を代表する作品の1本になったとの評は過言ではないだろう。
実はこの『シン・ゴジラ』、東宝にとって、これまでのゴジラシリーズにも増して、重要な位置づけにあった。なぜなら、東宝が大きく掲げるゴジラの方針、いわば「ゴジラ戦略」の中核を成しているからだ。
東宝は14年10月に社内組織として「ゴジコン(ゴジラ戦略会議)」を発足。ゴジラに関する情報を集約し、キャラクターとしてのゴジラをさらに育て、収益機会の拡大を目指している。また、15年4月に発表した中期経営戦略では、ゴジラのキャラクター展開に重点投資する考えを表明。中期戦略に書かれた映画作品やキャラクター名は「ゴジラ」以外はなく、東宝におけるゴジラのプライオリティの高さを明示していたのだった。
こうしたゴジラ戦略のもと、『シン・ゴジラ』は製作・公開。それに連動し、ゴジラ版権の積極的運用、劇場用アニメ作品の製作、ハリウッド版ゴジラのシリーズ化、新宿歌舞伎町のゴジラヘッド、それ以外にも多種多様な種が蒔かれ、これから互いに成長し合うことが求められる。そんな状況下で、映画の特大ヒットによって、東宝のゴジラ戦略は好循環に向けて幸先の良いスタートを切ったのだった。
今回の特集では、東宝のゴジラ戦略に肉薄する。その全体像をしっかり捉えつつ、4人のキーマンにインタビューを実施。まずは『シン・ゴジラ』の製作面と宣伝面に迫り、さらにハリウッド版への関わり、アニメ版の進捗、新宿東宝ビルと歌舞伎町の現状、拡大するゴジラ版権など、ゴジラをめぐる現在と未来を様々な角度から照射していく――。
“時代が要請してくれた”
『シン・ゴジラ』は、総監督・脚本を「エヴァンゲリオン」シリーズの庵野秀明、監督・特技監督を樋口真嗣、准監督・特技統括を尾上克郎が務めた、まったく新しいゴジラ映画だ。
 今の日本に初めてゴジラが現れた時、我々はいったいどうなるのか。そうしたテーマ性、徹底した取材に基づいた迫真のストーリー、ゴジラの造形を含む映像の持つ吸引力、庵野総監督以下のスタッフ構成、主役級が居並ぶ328人ものキャスト陣と、規格外の映画として完成した。エグゼクティブプロデューサーとして『シン・ゴジラ』の製作面を束ねたのが、映画企画部の山内章弘部長(=写真)だ。
今の日本に初めてゴジラが現れた時、我々はいったいどうなるのか。そうしたテーマ性、徹底した取材に基づいた迫真のストーリー、ゴジラの造形を含む映像の持つ吸引力、庵野総監督以下のスタッフ構成、主役級が居並ぶ328人ものキャスト陣と、規格外の映画として完成した。エグゼクティブプロデューサーとして『シン・ゴジラ』の製作面を束ねたのが、映画企画部の山内章弘部長(=写真)だ。――日本版の前作『ゴジラ FINAL WARS』の公開が2004年12月。『シン・ゴジラ』まで長らく休眠しました。この間、東宝の社内はどんな状況でしたか。全社的にいつかゴジラを作ろうという確固たる決意があったのか、それとも、一部の人が思っていただけなのか。
山内 人によって温度差があるでしょうけど、具体まで至らなかったのはそういう機運がなかったということだと思います。それに、社内でいくらやろうと言っても、世の中から欲してもらわないと見向きもされませんから、12年の月日は必要だったんだと思います。
――ハリウッド版『GODZILLA』が製作され14年7月に公開。その後、同じ年の12月に日本でも新しいゴジラを製作するとの情報を発表しました。
山内 ほぼ10年休眠状態の中で作るべく機運が高まったのは、ハリウッド版はもちろんですが、東日本大震災も大きかったかもしれません。沢山あるゴジラ映画が全部そうではないかもしれませんが、ゴジラは日本を覆う不安感の象徴です。初代『ゴジラ』(1954年)は、戦後日本がまだ貧しく外圧があり、これからどっちに進んでいくのかという不安。また『シン・ゴジラ』は2回目でしたが、リブート1回目の『ゴジラ』(84年)は、バブル前夜のザワザワした日本がどこに向かうのかという漠然とした不安。今回は震災があったから作ったというわけではないですが、不安感を象徴するゴジラ、それに対峙していく日本を見たいという気持ちになってきていたのだと思います。『FINAL WARS』の翌年にもう1回やろうとしても、難しかったでしょう。格好よく言えば、時代が要請してくれたんじゃないですかね。
――7月19日の完成報告会見での山内さんの発言によると、『シン・ゴジラ』は12年末から始動したとのことですね。本当にゴジラの新作を作るぞと、社内で動き出したのは誰でしたか。
山内 市川(南取締役)と私ですね。
――この時点で、庵野秀明さんに打診しようというのは。
山内 庵野さんは、真っ先に名前が挙がった人でした。12年ぶりに復活させるとなれば「なぜ作るのか」と大きな注目を浴びるのは必至です。その時に「この人だから作るんです」と日本だけじゃなく世界でも納得し得る人じゃないといけません。庵野さんは「エヴァンゲリオン」で世界的に受け入れられているし、特撮や怪獣ものに対する造詣も深い。実写映画の経験もある。色んな状況を考えると、庵野さんしかいないんです。でも、エヴァの新作が待機している中で、難しいだろう。こちらの声掛けも普通だったら断られる。僕らもダメ元でした。最初は、監修や総監督でもいいので、コンセプトのところに庵野色が出る形をなんとか実現できないか。これが、最初の話です。
――13年の年明けに市川取締役が庵野さんに話をし、すぐに快諾ではなかったけれども、同年春には合意し本格始動したんですね。
山内 庵野さんが社長を務める会社「カラー」の中でも、庵野さんがゴジラに関わることは、ある時期まではトップシークレットでした。カラーでは、エヴァの新作も控えてますからね。
――庵野さんは総監督・脚本とクレジットされましたが、庵野さんが関わることが決まって以降、具体的にどのようなやり取りを行ったのですか。
山内 庵野さんは当時、はっきりと「怪獣映画は1作目のゴジラ1本あればいい。新しいものを作る必要はない」と話していました(笑)。でも、やるからには、1作目を超えるものにしたい。現代の日本にゴジラが初めて現れたら、今の日本はどう対峙するのか、というリアルシミュレーションものにしよう。こういう話が、最初の話し合いの段で出ていました。その合意を経て、庵野さんが企画メモのようなものを書いて、そこから走り始めました。
続きは、文化通信ジャーナル2016年11月号「特集 東宝のゴジラ戦略」に掲載。

