 株式会社クロックワークス:配給営業アシスタント
株式会社クロックワークス:配給営業アシスタント- 【注目!!】アイマックスジャパン株式会社:Associate Manager, Local Language Marketing アソシエイトマネージャー、ローカルランゲージマーケティング
- 【注目!!】mov株式会社:①コンテンツビジネス法務担当②コンテンツ海外販売・流通担当③字幕翻訳・ローカライズ担当④国際事業統括マネージャー⑤財務担当 ※CFO候補⑥事業推進マネージャー ※COO候補
- 【注目!!】株式会社クロックワークス:制作アシスタント
- 【注目!!】株式会社フラッグ:①パブリシスト(オフライン/オンライン)②デジタルプロモーションプランナー③広告プランナー④デスク
- 【注目!!】株式会社K2 Pictures:①配給 劇場営業(セールス)②宣伝(プロデューサー、AP、制作宣伝)③総務・経理(デスク担当)④商品化担当
- 【注目!!】松竹ナビ株式会社:①映画宣伝②アドバタイジング業務
- 【注目!!】映画ランド株式会社:(1)セールス(映画館向けSaaSシステムの営業 / インサイドセールスメイン)(2)カスタマーサポート(映画館向けSaaSシステムの営業 / カスタマーサクセス職候補)
インタビュー
最新記事
観察映画第6弾『牡蠣工場』想田和弘監督

『牡蠣工場』想田和弘監督
想田和弘監督の最新作ドキュメンタリー『牡蠣工場』が2月20日全国順次公開される。
岡山県・牛窓にある牡蠣工場の現状を描いた作品。牛窓は広島に次ぐ全国有数の牡蠣の産地。養殖された牡蠣の殻を取り除く「むき子」の仕事は代々地元の人々が担ってきたが、かつて20軒近くあった工場は今では6軒に減るなど、過疎化による労働力不足が課題となっている。工場には様々な人間がいる。東日本大震災の影響で宮城県から移住してきた人、実習生として働く2人の中国人青年、彼らを束ねる工場長。想田監督はそれら全てを内包した牡蠣工場にピントを合わせた。
想田監督は台本やナレーション、BGM等などを一切排した「観察映画」という理論を提唱、実践する映画作家。観察映画のフィルモグラフィーには『選挙』『精神』『演劇1』『演劇2』『選挙2』が並ぶ。観察映画シリーズ第6作『牡蠣工場』における、その理論とは。
牡蠣工場に放り込まれたかの様に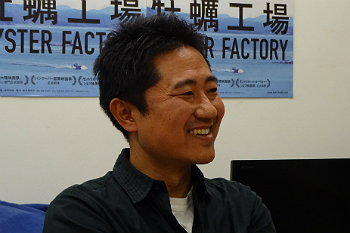 ――観察映画から受けた印象は、「映画に必要なものを撮っていく」というよりも「撮ったものが映画になっていく」というものでした。
――観察映画から受けた印象は、「映画に必要なものを撮っていく」というよりも「撮ったものが映画になっていく」というものでした。
想田監督(=右写真) まさにそういった感覚です。観察映画の「観察」とはよく見る、よく聞くということです。その結果、発見したことや出会ったことを映画にしていくという方法論です。
――テーマは仰仰しいものではなく、「観察映画を撮ること、それ自体」に向けられている様に感じました。
想田監督 そうですね、少なくとも最初にテーマを定めて作った作品ではありません。「牡蠣工場の世界を丸ごと描きたい」という欲求を持って制作しました。後継者不足や移民問題、震災の影響などは牡蠣工場全体を描く上で大事な要素ではありますが、それがすべてではありません。
なので、『牡蠣工場』に社会的メッセージやプロパガンダ的要素を期待されるとガッカリされるかもしれません。テーマ主義的に作っていませんし、従ってテーマ主義的に観て頂くというよりも、あたかも牡蠣工場に放り込まれたかの様にその世界を体感して頂きたい。
未知のものに対して身体を開いておく
――牡蠣工場を撮ろうと思われたキッカケを教えて下さい。以前より気にかけられていた問題なのでしょうか。
想田監督 ひょんなことから生まれた映画でした。私は常時20個ほど映画のアイデアを持っていて、パソコン上でリストを作っていますが、それぞれはひと言メモの様なものです。ご縁のできたところから撮っていくわけですが、『牡蠣工場』となった企画は始め、「漁師」と書いてあっただけでした(笑)。
牛窓は妻の母親の出身地で、よく夏休みを過ごしていました。そこでたまたま漁師の方々と知り合いました。彼らのお話を聞いていると漁師の生活は経済的に厳しく、後継者の不在に悩み、数もだんだん減ってきているとのことでした。
そういう話を聞きながら水産物への需要はこれからも増えそうなのに、なぜ漁師さんは儲からないのか?という疑問が浮かび上がりました。そこである漁師さんに映画の撮影を申し込んだところ、承諾して頂きました。その後11月にカメラを持って伺いました。
ところが彼は「今は牡蠣のシーズンだよ」とおっしゃったのです。 ――つまり牡蠣以外の漁業は撮れないと。
――つまり牡蠣以外の漁業は撮れないと。
想田監督 そういうことです(笑)。もともと牡蠣工場を撮ることは頭の中に全くありませんでした。魚を獲る漁師についての映画をなんとなくイメージしていましたし、もっと言えばその漁師さんが牡蠣工場をお持ちだという事もその時に知ったぐらいでした。しかしだからと言って、撮影を中止するわけではありませんでした。
――何故でしょう。通常であれば、仕切り直しということもあり得るのではないでしょうか。
想田監督 もし私が観察映画と無縁の作家ならば、イメージに合わないという理由でそこで撮影を止めていたかもしれません。しかし、むしろ私はそのアクシデントを歓迎し、気持ちをすぐに切り替えて撮影を開始しました。
なぜなら観察映画の根幹には、未知のものに対して身体を開いておくという考え方があるからです。何が起きても、その流れに逆らわずに乗っていく、どこに連れていかれるのか自分も分からないけど踏み出していく。目的地の無い旅のようなものです。
わずかな「さざ波」をも見逃さない
――牡蠣工場を撮るつもりで無かったということは、つまり宮城の人や中国人実習生とは撮影中に出会ったという流れでしょうか。
想田監督 そうです。最初は、牡蠣の殻を剥く作業の風景を撮っていました。するとカレンダーの横に貼ってあるメモに気付きました。「11月9日、中国来る」と書かれている。「どういう意味だろう?」と思って皆さんの会話に聞き耳を立てていたら、「どうやら9日に中国人が労働者として来るらしい」ということが分かりました。
――そういった気付きの連続によってカメラが向けられていった映画だと受け止めています。しかし撮影を始めたはいいものの、何も撮れないことや完成できないこともあるのでは。
想田監督 理論的にはあり得ますよね。ただ私の経験では何もなかったから撮影を中止したり、映画が完成しなかったということはありません。必ず何かしら面白いことが起こっています。
それはハリウッド映画で起こるような大事件ではありませんが、必ず何かが起こっています。私は刺激のレベルを小さいレベルに設定しているだけです。例えば「サラリーマンが電車に乗り遅れそうになって、飛び乗る」、これだけでもスリルとサスペンスです。そう考えてみると日常では毎日必ずドラマが起きていて、「さざ波」が立っています。そのわずかなさざ波をも見逃さない様にすると、必ず何かが映り込みます。私はネタの強弱ではなく、いかに見るか、聞くかを大切にしながら映画を撮っています。 ――『牡蠣工場』でも被写体が「さざ波」を立たせる様なシーンが幾つもあったかと思います。特に中国人実習生が工場に到着する場面が印象に残っています。工場のおばちゃんたちが床掃除をしているシーンです。実習生は言葉が分からず、新しい環境に不安も抱いていたでしょう。そんな中、何か手伝おうと掃除用具に手を伸ばすアクション、想田監督はあそこで寄りますね。
――『牡蠣工場』でも被写体が「さざ波」を立たせる様なシーンが幾つもあったかと思います。特に中国人実習生が工場に到着する場面が印象に残っています。工場のおばちゃんたちが床掃除をしているシーンです。実習生は言葉が分からず、新しい環境に不安も抱いていたでしょう。そんな中、何か手伝おうと掃除用具に手を伸ばすアクション、想田監督はあそこで寄りますね。
想田監督 あのシーンの場合、23年前にニューヨークに移住した私の経験が活きました。私と中国人実習生の彼は「言葉が分からない所に飛び込んでいく」という共通の経験をしている訳ですね。そういった場では全身を目にして、皆が何をやっているかを観察すると同時に、私は役に立つ人間で敵意がない人間だということを必死にアピールしなければなりません。
あの時、私はその経験を思い出しながらカメラを回していました。だから彼が何か手伝おうとして掃除用具に手を伸ばす仕草には、ひときわ注目しましたし、そのアクションをカメラで追いました。彼の中で立ったさざ波を見逃さなかった訳です。私はそういうアクションをしている彼に気付き、映像へと翻訳しました。
観客との対等なコミュニケーション
――ある種、主観的な作品とも言えるのではないでしょうか。
想田監督 おっしゃる通りです。観察映画にはナレーションもテロップもないので、客観的だと誤解されがちですが、実は徹底的に主観的です。
カメラを回す時は「観察する→気付いたことを映像に翻訳する」の2段階を意識しています。何に気付くかは人それぞれ異なるので、同じ条件下で、同じ被写体を私以外の人間が撮ったとすると、全く異なる作品になるはずです。当たり前の話ですが、被写体との関係性や出会いは撮る人によって必ず異なります。そういった意味でも主観的な造りになる訳です。
――最後に観察映画に出会っていない観客に対して一言頂けますか。
想田監督 映画を通じてやりたいことは、観客との対等なコミュニケーションです。よく自分のことをピッチャーになぞらえます。観客はキャッチャーではなくバッター。私が投げるボールをただ受け止めるのではなく、能動的に打ち返してほしいんですね。『牡蠣工場』でも色々な方向に打ち返してほしいと願っております。
――更なるご活躍を期待しております。ありがとうございました。
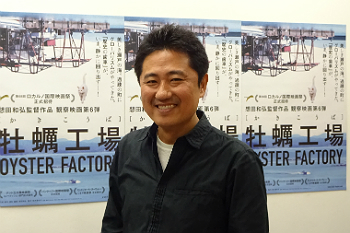 ◆想田和弘監督の略歴
◆想田和弘監督の略歴映画作家。70年生まれ。東京大学文学部宗教学・宗教史学科卒。スクール・オブビジュアルアーツ映画学科卒。93年からニューヨーク在住。NHK等のドキュメンタリー番組を40本以上手掛けた後、観察映画の方法を提唱・実践する。
◆『牡蠣工場』
http://www.kaki-kouba.com/
2月20日よりシアター・イメージフォーラムほか全国順次公開。監督/製作/撮影/編集:想田和弘、製作/柏木規与子、2015年/日本・米国/145分/DCP/(C)Laboratory X Inc./配給・宣伝:東風

