 株式会社クロックワークス:配給営業アシスタント
株式会社クロックワークス:配給営業アシスタント- 【注目!!】アイマックスジャパン株式会社:Associate Manager, Local Language Marketing アソシエイトマネージャー、ローカルランゲージマーケティング
- 【注目!!】mov株式会社:①コンテンツビジネス法務担当②コンテンツ海外販売・流通担当③字幕翻訳・ローカライズ担当④国際事業統括マネージャー⑤財務担当 ※CFO候補⑥事業推進マネージャー ※COO候補
- 【注目!!】株式会社クロックワークス:制作アシスタント
- 【注目!!】株式会社フラッグ:①パブリシスト(オフライン/オンライン)②デジタルプロモーションプランナー③広告プランナー④デスク
- 【注目!!】株式会社K2 Pictures:①配給 劇場営業(セールス)②宣伝(プロデューサー、AP、制作宣伝)③総務・経理(デスク担当)④商品化担当
- 【注目!!】松竹ナビ株式会社:①映画宣伝②アドバタイジング業務
- 【注目!!】映画ランド株式会社:(1)セールス(映画館向けSaaSシステムの営業 / インサイドセールスメイン)(2)カスタマーサポート(映画館向けSaaSシステムの営業 / カスタマーサクセス職候補)
インタビュー
最新記事
インタビュー:福原英行 東映(株)専務取締役不動産部門担当
30億円を投資し再開発、年間動員100万人目指す
東映は1975年開業の「東映太秦映画村」に30億円を投入して開村以来初の大規模なリニューアルを実施した。ポイントは①「撮影所口」を設けJR嵯峨野線「太秦駅」からのアクセスの短縮を図った②新アトラクション「からくり忍者屋敷」「東映アニメミュージアム」「浮世絵美術館」を新設等。開発を担当した同社の福原英行専務取締役に再開発の狙いや第2弾計画等について聞いた。
ピークは年間261万人
──東映太秦映画村は1975年に開業したわけですが、大体ピークは何年で、年間どの位の売上をあげていたのですか。
福原 1982年ですね。この年は年間動員261万人で、61億円の営業収入を記録しています。
──そこがピークで、その後下がっていったということですか。
福原 そうですね。1978年から16年間、年間動員200万人をずっと維持していたのです。
──200万人を割ったのはいつでしたか。
福原 1995年に200万人を割り、2000年以降も減り続け現在は100万人をも割っている状況です。しかし、オープンして35年がたち、累計営業収入は1500億円を超えており、もう一度、再生したいということで、今回のリニューアルになったわけです。
──年間動員100万人を超えたいということですね。
福原 そうです。今、80万人を少し切っているので、もう一度100万人を超えることを目指しています。
──今回のリニューアルはどんなコンセプトで実施したのですか。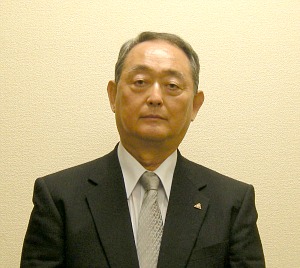 福原 名称は「東映太秦映画村」ですが、実際の中身は京都の映画村であり、これまで時代劇を中心に展開してきました。開村当初は故大川橋蔵さんのテレビ時代劇「銭形平次」全盛のころで、平均視聴率が常時20%を上回る大変な人気番組でした。おかげさまで、年間動員200万人を16年維持できていたのですが、時代劇の人気も少しずつ下降線を辿り、入場人員も80万人を割るところまで減少したのです。岡田社長は2年程前から「このまま時代劇だけ当て込んでいたら、数年後には川の先にある滝に落ちるぞ。何か新しいものを導入しなければダメだ」という意見を盛んに話していました。今回のコンセプトは、京都や太秦にとらわれずに“東映の映画村”というコンセプトで考えて欲しいということでした。東映には「仮面ライダー」シリーズや“戦隊もの”、アニメーションといったヒーローものがお客様から強く指示されており、時代劇にとらわれずに、東映グループのコンテンツを積極的に展開するコンセプトでプランニングしたわけです。
福原 名称は「東映太秦映画村」ですが、実際の中身は京都の映画村であり、これまで時代劇を中心に展開してきました。開村当初は故大川橋蔵さんのテレビ時代劇「銭形平次」全盛のころで、平均視聴率が常時20%を上回る大変な人気番組でした。おかげさまで、年間動員200万人を16年維持できていたのですが、時代劇の人気も少しずつ下降線を辿り、入場人員も80万人を割るところまで減少したのです。岡田社長は2年程前から「このまま時代劇だけ当て込んでいたら、数年後には川の先にある滝に落ちるぞ。何か新しいものを導入しなければダメだ」という意見を盛んに話していました。今回のコンセプトは、京都や太秦にとらわれずに“東映の映画村”というコンセプトで考えて欲しいということでした。東映には「仮面ライダー」シリーズや“戦隊もの”、アニメーションといったヒーローものがお客様から強く指示されており、時代劇にとらわれずに、東映グループのコンテンツを積極的に展開するコンセプトでプランニングしたわけです。
具体的には、まず京都撮影所の南側入口に「撮影所口」を新設し、駅からのアクセスの利便性を図りました。これまでの撮影所入口はJR嵯峨野線「太秦駅」から約1200メートルの距離があり、徒歩で15分から20分以上かかっていました。冬は寒い、夏は暑い中を家族連れが歩いて来たわけです。私どもも、これまでお客様に負担をかける動線で来たことを反省しまして、今度の「撮影所口」では約350メートルに短縮し、駅から5分で着くことになりました。
太秦駅からの距離を短縮
──この撮影所口から映画村まではどのくらいあるのですか。
福原 実際には200メートル以上あり、単なる通路を作るだけでなく、お客さまに撮影所の雰囲気を体感してもらうスペースにしようと、大道具倉庫の裏にショーウィンドウを作って、衣装を飾ったり、小道具を飾ったりして、見ながら入村してもらう動線にしました。それにもう一つ、東映の映画村というコンセプトであり、「東映アニメミュージアム」を作りました。当初、日本全体の「アニメミュージアム」という考えもありましたが、資料的な問題もあり、東映アニメーション㈱のミュージアムという形態で、東映アニメーションの歴史を中心にして、長編アニメ映画「白蛇伝」(’58)から「プリキュア」「ワンピース」までポスター90数点を掲示しました。それから今はデジタルの時代でセル画は使わないのですが、アナログ時代のセル画を70数点展示しました。ミュージアムの構成は、2部屋に分かれ、もう1部屋が参加型で、DVDシアターとアフレコ・ルームを設け、お客さまに選んでもらって「プリキュア」と「ゲゲゲの鬼太郎」のアフレコを体験してもらうコーナーを設置しました。 (つづく)
※インタビュー全文は「文化通信ジャーナル」2011年10月号に掲載

