 株式会社クロックワークス:配給営業アシスタント
株式会社クロックワークス:配給営業アシスタント- 【注目!!】アイマックスジャパン株式会社:Associate Manager, Local Language Marketing アソシエイトマネージャー、ローカルランゲージマーケティング
- 【注目!!】mov株式会社:①コンテンツビジネス法務担当②コンテンツ海外販売・流通担当③字幕翻訳・ローカライズ担当④国際事業統括マネージャー⑤財務担当 ※CFO候補⑥事業推進マネージャー ※COO候補
- 【注目!!】株式会社クロックワークス:制作アシスタント
- 【注目!!】株式会社フラッグ:①パブリシスト(オフライン/オンライン)②デジタルプロモーションプランナー③広告プランナー④デスク
- 【注目!!】株式会社K2 Pictures:①配給 劇場営業(セールス)②宣伝(プロデューサー、AP、制作宣伝)③総務・経理(デスク担当)④商品化担当
- 【注目!!】松竹ナビ株式会社:①映画宣伝②アドバタイジング業務
- 【注目!!】映画ランド株式会社:(1)セールス(映画館向けSaaSシステムの営業 / インサイドセールスメイン)(2)カスタマーサポート(映画館向けSaaSシステムの営業 / カスタマーサクセス職候補)
人気記事デイリーランキング:26年02月26日集計
エンタメ・トピックス
最新記事
日本映画復興会議50周年記念集会
2011年05月21日
50年の活動をふまえて新しい探究の時代へ―
「日本映画復興会議50周年記念集会」が去る5月21日、東京・南青山のNHK青山荘で開催された。本会議は、「日本の映画文化と映画産業を民主的に復興し、発展させること」を目指して活動する映画人、製作プロダクション、配給会社、鑑賞団体、映画団体、映画会社、映画労働組合、映画愛好家が集まって設立された。
今回のテーマは「50年の活動をふまえて新しい探究の時代へ」。まず、羽渕三良事務局長(写真下左)が開会・集会議長団(梯幹事と野村幹事)を確認し、大澤豊代表委員(写真下右)が独立プロの歩み、本会議がどのような経緯で設立され、「50年の総括として検証しながら歴史の重みを振り返りつつ、今後の展望を含めて激論したい」と挨拶した。

そして、日本大学映画学科教授の田島良一氏(写真下左)が「日本映画の現在―戦後66年の歩み―」と題して記念講演。田島氏は、1960年代から10年単位で日本映画の歩みを以下の通り概要説明した。(田島氏配布資料参照)
①1960年代 映画産業の斜陽化―量産から減産へ
②1970年代 撮影所システム(自社製作映画を量産)の終焉
③1980年代 自主映画ブームと新たな模索
④1990年代 日本映画の危機
⑤2000年代 日本映画の「再生」
田島氏は最後に、「ODS(非映画コンテンツ)の上映がシネコンを中心に増えているが、そもそも映画館とは映画だけを見せるところではなかったので、原点に戻ったと言えるのではないか」と締め括り、質疑応答へ。
続いて、日本映画製作者協会副理事長の岡田裕氏(アルゴ・ピクチャーズ代表取締役)が「独立プロの映画の製作は今?」と題して特別報告を以下の通り行った。
 ◆旧来の映画制作とTV局映画の違い
◆旧来の映画制作とTV局映画の違い~撮影所システムの崩壊、TV局映画の製作へ
・1971年が象徴的。大映が倒産、日活がロマンポルノへ、東宝が製作を切り離す。
・80年代に入り、レンタルビデオ店が映画の新しい出口として登場。
・2次使用、3時使用でどうにか生き延びてきた。
・90年代に入って、映画制作の現場が非常に厳しくなっていく。
・アルゴ・プロジェクト~6つのプロダクションがルールを作って92年まで活動。
・サントリーなど、文化活動として企業が参加し支える。
・TV局映画時代に入る。初期はフジテレビが先導、映画界の人材で作られた。
・98年から「踊る大捜査線」前の参加の仕方と根本的に違ってくる。
・新しいメディアの登場で、広告収入が減少。放送外収入で儲ける。
・大衆に対するマーケティング力。何を好んでいるか。データ調査を徹底的に。
・映画会社は、TV局映画をすばやく取り入れた。
・昨年の年間興収2200億円のうち約700億円が東宝配給作品。
・TV局映画中心、東宝マーケットで支えられている。
・必ずしも当たるものがいい作品ではない。芸術的、文化的価値のあるものは―。
・当てること、果たしてそれだけでいいのか? 両方を兼ね備えるには―。
・決して映画は情報(コンテンツ)ではなくて、質の差があると思う。
◆作り方の微妙な違い
・映画作りにはムダがあって、今後の映画制作に残していかなくてはいけない。
・極端に意欲的な映画は、映画ビジネスを支える上でも絶対に必要。
・作り手に権利が残るような、興行・配給との分配のあり方について。
・再生産できるようなシステム作りをしていかないといけない―など。
質疑応答に続いては、「日本映画復興会議50年―その歩みと現在の課題―」について桂壮三郎代表委員(写真下)が報告を行った。

・10年単位にまとめた映画産業をめぐる特徴と日本映画復興会議の活動
・日本映画復興会議50周年に寄せて
・映画産業と日本映画復興会議50年の年表など。
そして、全国からの参会者たちと討論を行って閉会した。
第28回日本映画復興賞・50周年記念復興賞贈呈式&祝賀会

午後には「第28回日本映画復興賞・50周年記念復興賞」贈呈式と祝賀会が開催され、日本映画復興賞受賞の仲代達矢、「アンダンテ~稲の旋律~」の金田敬監督、加藤周一映画製作実行委員会の代表、奨励賞受賞の「月あかりの下で ある定時制高校の記憶」の太田直子監督、「トロッコ」の片原朋子プロデューサー、「パートナーズ」の下村優監督、特別賞受賞の故・橘祐典(映画監督)のご夫人、さらに50周年記念復興賞受賞の新藤兼人監督、山田洋次監督、そして山田和夫氏(病気療養中)のご夫人らが出席。祝賀会の乾杯の音頭を山本洋プロデューサーがとった。
 ▼新藤兼人監督の話 昨年の夏過ぎに山田和夫さんと会い、ロシアの映画人協会から感謝状をもらったことを大変喜んでおりました。ロシア人よりロシア映画に詳しい山田さんに、ロシアはもっと早く感謝状を贈るべきだったと思っていたので、私も嬉しく共に喜びました。その後、病に倒れられて大変残念ですが、日本の映画人にもわかりやすいロシア映画に関する本を執筆されることを今も望んでおります。
▼新藤兼人監督の話 昨年の夏過ぎに山田和夫さんと会い、ロシアの映画人協会から感謝状をもらったことを大変喜んでおりました。ロシア人よりロシア映画に詳しい山田さんに、ロシアはもっと早く感謝状を贈るべきだったと思っていたので、私も嬉しく共に喜びました。その後、病に倒れられて大変残念ですが、日本の映画人にもわかりやすいロシア映画に関する本を執筆されることを今も望んでおります。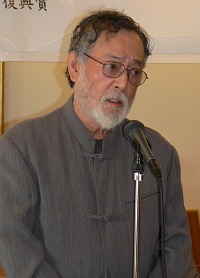 ▼仲代達矢の話 60年映画の役者をやっておりますが、最初にカメラの前に立ったのが、日本映画復興会議の発起人の一人である山本薩夫監督の作品でしたので、本当に嬉しく思っております。日本映画も不毛な状態のところがあると思いますが、次世代の映画作りの人たちに、頑張って頂きたいと思っております。
▼仲代達矢の話 60年映画の役者をやっておりますが、最初にカメラの前に立ったのが、日本映画復興会議の発起人の一人である山本薩夫監督の作品でしたので、本当に嬉しく思っております。日本映画も不毛な状態のところがあると思いますが、次世代の映画作りの人たちに、頑張って頂きたいと思っております。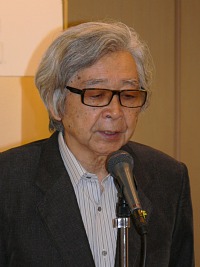 ▼山田洋次監督の話 初めて映画の世界に足を踏み入れたのは、大学時代に山田和夫さんが作った映画研究会がきっかけ。当時、独立プロ運動が起きた時期でしたから、エキストラとして参加し、羨望の思いで見ていたのを思い出します。
▼山田洋次監督の話 初めて映画の世界に足を踏み入れたのは、大学時代に山田和夫さんが作った映画研究会がきっかけ。当時、独立プロ運動が起きた時期でしたから、エキストラとして参加し、羨望の思いで見ていたのを思い出します。(了)

